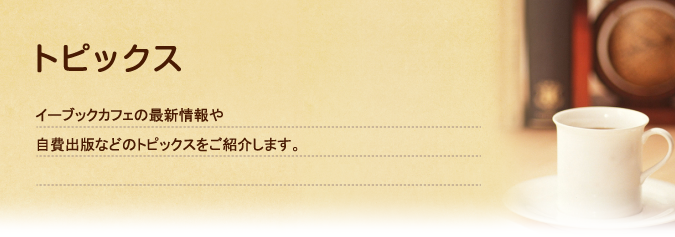梶井基次郎の小説「檸檬」に出てくる果物屋さん「八百卯」を訪ねて
「えたいの知れない不吉な塊(かたまり)が私の心を始終圧(おさ)えつけていた」という印象的なフレーズから始まる、梶井基次郎の短編小説「檸檬(れもん)」。
何かに追い立てられるように、街から街へさまよう主人公の「私」が、ある果物屋でレモンを買い、その後、丸善書店に立ち寄ります。様々な色彩の画本を積み上げて、その頂(いただき)に袂(たもと)から出したレモンをそっと置き、何食わぬ顔で店から出る「私」。
シンプルなストーリーながらも、瑞々しい文章で読者に強烈な余韻を残すこの小説は、1925(大正14)年に雑誌で発表されてから、もっぱら若者に愛読されてきたそうです。昭和初期の文学青年は、「檸檬」がおさめられた本を片手に、「私」に感情移入しながら、彼がさまよった街を歩いたとか…。
主人公が、「爆弾」として「丸善」に仕掛けたレモンを買ったのが、寺町二条の角に佇む、果物屋「八百卯」さんです。
残念ながら「丸善」は、2005(平成17)年10月に閉店してしまいましたが、こちらの「八百卯」は懐かしい雰囲気を残しつつ、現在も果物、さらにフルーツの雑貨などを扱っています。
店の一角にある「梶井基次郎 檸檬コーナー」ともいうべきスペースには、レモンの鮮やかなイエローに混じって梶井の関連記事が飾ってあり、31歳という若さで亡くなった彼へ思いを馳せることができます。
「その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。其処は決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感ぜられた。……」と、「私」が絶賛する「八百卯」。
この果物屋さんは、小説「檸檬」において、第二の主役とも言える存在なのではないでしょうか。
日常生活で、「えたいの知れない不吉な塊」を少しでも感じたら、かつての文学青年のようにこちらを訪れて、「私」に思いを重ねてみるのも良いかもしれません。
ちなみに二階はフルーツパーラーになっていて、果物たっぷりのスイーツが味わえますよ。
(データ)
●梶井基次郎/かじいもとじろう(1901−1932)
『檸檬』、『城のある町にて』、『泥濘』、『路上』、『ある心の風景』、『櫻の樹の下には』、『ある崖上の感情』 など
●八百卯
京都市中京区寺町二条角(地下鉄東西線「市役所前」駅よりすぐ)
■2009年1月25日、残念ながら創業130年の歴史に幕を下ろしました。

思わず足を止め、見入ってしまう「梶井基次郎 檸檬の店」アピールコーナー。